子育て中の親であればみんな“わが子が元気で健康に成長していく”ことを願うものですよね。
最近では“多動児”や、“発達障害”という言葉をよく耳にするようになりました。
少し前までは“ちょっと変わっている”というあつかいをされていた子供でも、医学の進歩により病名がつくようになったのです。
そのため、ここ10年くらい世間の認知度も高くなり、支援なども充実してきています。さらに、大人のADHDも認知されてきています。
それだけ広く知れ渡っているからこそ、自分の子供は多動児の特徴と一致しているかも!? と不安になる親御さんも多いといわれています。
実際に、多動児といわれる子供はどのような特徴があるのか? ADHDの子供への接しかた、病院選びや薬の話。セルフチェック表も掲載しています。できるだけわかりやすくお伝えしますね。
発達障害のお子さんをもつ親御さんが書いたブログも参考になりますよ。

多動児の特徴とADHD
まず、多動児という言葉を検索してみると出てくるのが
ADHD(注意欠陥多動障害)(Attention-Deficit Hyperactivity Disorders)
という名前です。
ADHDは、不注意・多動性・衝動性の3つの症状の特徴をもつ障害になります。
これらは子供の行動にあらわれる症状であり、知能指数の優劣で判断されるものではありません。
ADHD(注意欠陥多動障害)の原因
ADHDの原因は、脳神経の機能不全によっておこる説が有力です。
最近では、“家族性”があると言われています。
家族性とは
- 遺伝性:病気の遺伝子を受け継ぎ親と同じ病気になる。
- 家族性:家族に糖尿病や目が悪い人がいると、子供もそうなる確率が高い。
アメリカだと、両親のどちらかがADHDの場合、子供にあらわれる確率が最大50%
子供の兄弟にADHDの子がいると、いない子に比べて5~7倍多くなると言われています。
しかし、環境(まわりの対処のしかた)で確率が大きく変わります。
ADHDの家族性のある一卵性双生児でも、ふたりとも発症する確率は100%ではないので環境による影響も考えられます。
出典:姫路駅前 心療内科 精神科 前田クリニック
「しつけが悪くて」と心配される親御さんもいらっしゃいますが、しつけのせいではありませんよ。

ADHD (注意欠陥多動障害)の男女比や発症頻度
- 男女比 4~6:1 で男の子が多いです。
- 発症頻度は、3~10%と推定されています。
出典: 自治医科大学
ADHD(注意欠陥多動障害)の症状の特徴
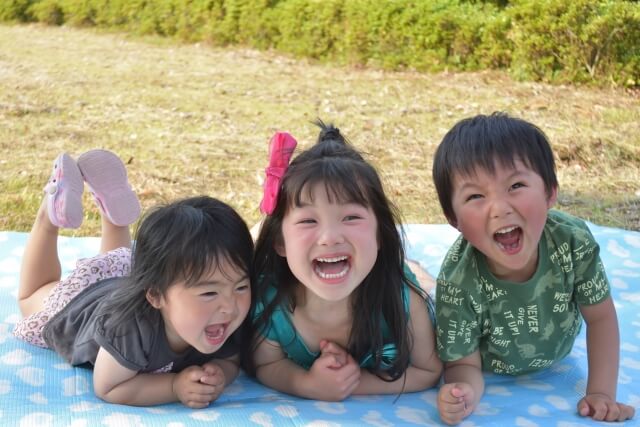
それぞれの症状の特徴をあげていきます。
不注意
- 忘れものが多く、ものを失くしやすい
- 整理整頓や片づけが苦手
- 集中力が途切れやすい
- 行動にとりかかるのが遅い
- 興味のあることになると、まわりがみえなくなる
多動性
- 授業中などおとなしく座っていられない
- 座っているときでも落ち着きがなく体を動かしてしまう
- 静かにしなければいけない場所で大声をだしてしまう
- 人から「落ち着きがない」と指摘される
- おしゃべりが止まらない
衝動性
- 順番を待つことができない
- 気にさわることがあるとすぐに手が出てしまう
- 人の会話の途中でもさえぎって自分の話をしたがる
- 人の邪魔をしたり、やろうとしていることを横取りする
- まわりの安全を考えずに行動をすることが多い
これらの症状は、人によってあらわれかたが違います。
ADHDは、これらの症状から大きく3つのタイプに分類されます。
ADHD(注意欠陥多動障害)の3つのタイプ
不注意優勢型
不注意の症状が強いタイプです。
- 忘れものが多い
- 集中力がない
- 整理整頓ができない
などは、小さい子供さんならよく見られることでもあります。そのため、なかなか症状に気づかないタイプともいえます。
ADHDに理解がない場合、「厳しくしかる」、「不注意を責める」ことにより子供が自信を失って、無気力や投げやりな態度をとってしまい不登校などの問題も出てきます。
多動性-衝動性優勢型
多動性、衝動性の症状が出るタイプです。
- 落ち着きがない
- じっと座っていられない
- すぐに大声をだしたり手が出たりする
- 人の話をさえぎって自分の話ばかりをする
ということが多いです。
混合型
混合型は3つの症状が全て出てしまうタイプです。
人によって強く出る症状は違いますが、ADHDの特徴としての判断はしやすいです。そのため、ADHDと診断をされている人の8割がこのタイプだとされています。
ただ、アスペルガーの症状との区別が付きにくい症状でもあります。
アスペルガーとは
コミュニケーション障害、対人関係の問題、限定されたものへの強いこだわりなどがある症状です。
ASD(自閉症スペクトラム)に分類される症状で、従来の自閉症との違いとしては、“知的障害をともなわない”ことが特徴です。
- 人とのコミュニケーションがうまく取れない
- ひとつのものへの強いこだわり
などの症状が、ADHDの混合型と似ているとされる点です。

ADHDの診断方法
ADHD(注意欠陥多動障害)の3つのタイプにあてはまる点があるからといって、必ずADHDというわけではありません。
ADHDの判断は専門の医療機関で診断を受ける必要があります。
診断は心理テストや行動観察になり、脳の画像診断、脳波などだけで診断はしません。しかし、いきなり病院に行くということに、抵抗を感じるという人も少なくありません。
簡単にできるチェックリストなどもありますので、参考にしてみましょう。
簡単なセルフチェックをご紹介します。
子供(児童)のAD/HDチェック
注意欠陥障害のセルフチェック表
2.速やかに身だしなみを整えることができない
3.朝食時に年齢相応の行動が取れていない
4.登校前に家族や兄弟とトラブルになることが多い
5.学校に行くのが好きではない
6.授業中に周囲の子供と同じ行動が取れていない
7.学校に友達が少ない
8.学校でのできごとを保護者にうまく伝えられない
9.同年代の友人が少ない
10.同年代と一緒に取り組むスポーツや課外授業に自信をもって参加できていない
11.家庭できちんと宿題をこなすことができない
12.家族と言い争いをすることが多い
13.落ち着いて食事ができない
14.保護者は子供と安心して買い物ができない
15.(12歳以上の場合)同年代との遊びやスポーツ、勉強を夜に行うのが難しい
16.(12歳未満の場合)親の指示に従うことができず、夜寝る前の本の読み聞かせなどが難しい
17.スムーズにベッドに入って寝ることができない
18.夜中に目覚めることが多い
19.自信がない、情緒が安定してないと感じられる
20.混乱や言い争いがなく過ごせる日が少ない
ハフィントンポストあくまで簡易的なセルフチェックです。安易に決めつけるのではなく、少しでも疑わしい場合、専門医に相談しましょう。
どこからが多動児になるのか?
子供というのは多かれ少なかれ、落ち着きがないものです。
小さいころはなおさらです。
では、どこからが多動児という判断になるのでしょうか? 1歳~3歳ごろはまだ、自分の世界が中心の時期です。
よほど目立った行動がないかぎり、1歳~3歳ごろで多動児と判断することは難しいです。
とくに知能指数が平均以上の場合は、乳幼児健診でも異常無しと判断されることがあります。
3歳以降になってくると、まわりとの違いで気づく点も増えてきます。
多動児ADHDの子供との接しかた
ADHDは、早期の発見で改善がみられる症状です。
最近では、幼稚園などでの発達の疑いのある子供には、先生のほうから親に病院での診断をすすめられることもあります。
家族や学校などとのサポートが大切です。
- 伝えるルールはわかりやすく
- 言葉以外にも見てわかるように絵や文字でルールを伝える
- 座る位置は、気が散る窓際はさける
- 具体的な表現で伝える(部屋を片づける→本は本棚に片づける)
- 成功体験を増やす。小さな課題や目標かたはじめる
- 量より質が重要。宿題などはだらだらと10問解くより、集中して5問解く。
- 家族だけでなく、友達や近所の人にもサポートしてもらう
- 行動表を壁に貼ったりタイマーを活用したり、時間を視覚的に意識してもらう
- 無理に長時間座らせようとしない
不注意優勢型の子供との接しかた
学校や人の前で、
- 「ダメ!ちゃんと集中しなさい!」
- 「また忘れものしたの!ダメじゃない!」
と厳しく注意するよりは、1対1の状態で注意をうながすほうが効果的です。
多動性-衝動性優勢型の子供との接しかた
ADHDは自分の行動を直すことが難しく、自分自身で気がついていない場合が多いです。
注意のしかたも「うるさい!」より、「小さい声でお話しようね」という声がけによって気づきをあたえましょう。
運動をしたあとは多動が落ちつく場合があります。
混合型の子供との接しかた
不注意優勢型と多動性-衝動性優勢型の混合になるので両方の接しかたが参考になります。

ADHDを含む発達障害は、早期発見することが大切です
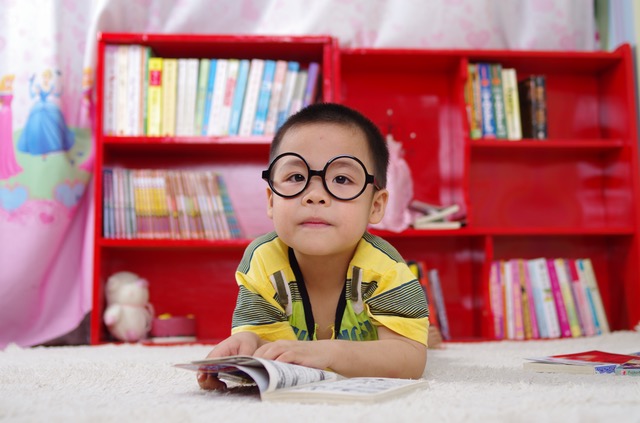
「うちの子がおかしいって言いたいの!?」
と過剰に反応してしまう親御さんもいるかもしれません。しかし、小学校に入ると周囲との差はより目立つようになってしまいます。
ADHDを含む発達障害は、早期発見することが大切です。
現在では、未就学児向けの療育園などのサポートも充実してきています。気になる点がある場合は、早めに対策していきましょう。
なにより、親がしっかりと障害について理解する必要があります。
まわりと違うからと、感情的に怒鳴ったり、無理やりおさえつけるという行動は逆効果です。
ADHDの子供さんは、言われたことを理解して判断するということが苦手なことが多いです。
- ルールや約束などをするときは、わかりやすい説明をしてあげましょう。
- ルールや約束を守れたときは、しっかりと褒めてあげましょう。
褒められることで、子供さんの自己肯定感を育ててあげてください。
子供の叱り方とほめ方【子供を劇的に伸ばすコツ!】自己肯定感をMAXにする

多動児ADHDを診察する病院の探しかた
全国の病院を検索できるサイトがあります。
小児のADHDの診察をする病院が検索できます。2017年4月24日現在で288件の病院がヒットしています。
多動児ADHDを診察する病院は何科になる?
診断してくれる病院は、“小児科”や“児童精神科”です。児童精神科は、総合病院や大学病院で設置しています。
専門医が近隣で見つからない場合、自治体を活用しましょう。
お住いの地域の市区町村の保健センターや、児童相談所に相談してみましょう。近くの専門医を紹介してくれます。
かかりつけの小児科があれば、まずは先生に相談するのもよいでしょう。
病院での診察は1度で結果が出るわけではないので通院できる距離がよいですね。
もし、診断結果に疑問や不安がある場合、セカンドオピニオンとして別の病院を受診するのも一案です。
ADHDの薬について
薬が唯一の治療法ではありません。環境を整えて親や学校などとの連絡連携が重要です。
薬にできないことがあります。頼りきるのはやめましょう。それぞれの子供に合わせたサポートが大切です。
薬にできること
落ちつかせる
集中時間を延長させる
衝動性を減らす
攻撃的な態度を緩和させる
抑うつ、不安感の減少
薬にできないこと
好ましい行動を理解し、増やす
対人関係や学習のスキルを学び、実践する
弱点を理解し、悪化した感情を改善する
成功体験を増やし、自信とやる気をもたせる
ADHDのある方達には、リタリン(メチルフェニデート)に代表される中枢神経刺激薬、抗うつ薬、抗けいれん薬、抗精神病薬が使われます。
効果がある場合は、症状がコントロールされているときに、心理教育的支援やよい環境作りを目指さねばなりません。
中略
なお、これらの薬は、現在はADHDに対して保険適応にはなっていません。リタリンに限らず、これらの薬は、医師の責任のもと、本人・家族への充分な説明と同意が必要になります。
えじそんくらぶキラッと注
えじそんくらぶのサイトに、詳しく“現在のADHD薬”について記載されていました。
現在、日本でADHDに効能・効果が承認されている薬はメチルフェニデート塩酸塩徐放錠(コンサータ)とアトモキセチン塩酸塩(ストラテラ)があります。
なお、コンサータが発売されるまで適応外で使われていたメチルフェニデート塩酸塩製剤(リタリン)は、現在ではナルコレプシーのみの適応となり、ADHDへの処方ができなくなっています。
えじそんくらぶ公式サイトコンサータとストラテラの効果について
コンサータとストラテラの小児期のADHDに対する効果はそれぞれ国内および海外での臨床試験で検証されていますが、コンサータは投与後直ぐに効果が見られ、約12時間で効果が消失し、アトモキセチンは投与後8週間ほどで効果が見られ、1日2回投与なので効果は24時間持続します。
主な副作用とその頻度は、コンサータでは食欲不振(33.3%)、初期不眠(13.4%)、体重減少(12.0%)、食欲減退(8.8%)、頭痛(8.3%)、不眠症(6.0%)、腹痛(5.6%)、悪心(5.6%)、チック(5.1%)、発熱(5.1%)、アトモキセチンでは頭痛(21.6%)、食欲減退(15.5%)、傾眠(14.0%)、腹痛(11.2%)、悪心(9.7%)です。
えじそんくらぶ公式サイトNHK朝イチ特集「シリーズ発達障害 “ほかの子と違う?” 子育ての悩み」
2017年7月24日放送の朝イチ特集は発達障害でした。
番組では小学6年生の女の子とそのご家族(古山さん)が紹介されていました。
古山さんは子供が泣き叫ぶと話を聞いてくれないので、落ち着くまで待つそうです。
そのときは“お手紙を渡す”を渡して部屋から出てくるのを待っていました。
発達障害(多動児)と、わがままの違い
発達障害にくわしい、鳥取大学大学院井上雅彦先生は、
厳密には難しい。線引するのではなく、どうやって工夫すれば努力が報われるか。
まわりが工夫する努力が必要だとコメントしています。
「片付けられない」も程度の問題。
→片付けかたがわからないだけかも。
「忘れものが多い」も頻度の問題
→工夫次第で頻度は減っていきます。
FAXの質問で「発達障害は治るのか?」との問いに、
井上先生は、「伝えかたなどを工夫することで障害があっても動きや考えがスムーズになっていく」と伝えています。
古山さんも生活をサポートする工夫をおこなっていました。
- 持っていくものを確認させるための持ちものボード
- 朝おこなう順番を確認できるカード
- 自分でおこなうことをゲーム感覚で理解させる
発達障害の子供を持つ親御さんはふつうに接してほしいと願っています
朝イチ特集には親の会代表の上野さんも出演されていました。
発達障害を持つ親の願いは「普通に接して欲しい」と伝えています。
- かわいそうと言われたくない。
- 毎回大変ね、と言われるのが辛い。
- 同情は止めて欲しい。
発達障害の診断検査はできるだけ早くおこないましょう
診断検査で発達障害とわかれば、親御さんはほっとします。
通常なら発達障害では無いほうがほっとするのでは?
そう思いますが、それまでは周りの理解がなく、自分のしつけや育てかたがダメだと悩んでいるママが多いためほっとすると、親の会代表の上野さんも伝えています。
地域によっては専門の病院(小児科、できれば専門医がいる)が無い場合もあります。しかし、ひとりで抱え込まず保育園や自治体の相談窓口を利用してください。
まとめ
子供さんがADHDの診断を受けたとき、自分の育てかたが悪かったのかと悲観する親も少なくありません。
しかし、ADHDは育てかたが原因でおこるわけではありません。
子供さんだって、お母さんを困らせたくて問題行動をしているわけではありません。
そのことをしっかりと理解してあげましょう。
参考
NPO法人:えじそんくらぶ小冊子『実力を出しきれない子どもたち』
著者:田中康雄(北海道大学大学院教育学研究科教授、児童精神科医)、高山恵子(NPO法人えじそんくらぶ代表)
コメント